 上野原は昔も今も高台にある街だ。街の中心地は甲州街道(国道20号)にあるが、桂側沿いの中央線からははずれている。駅と街はバスで行き来するが、これを歩くとなると結構疲れさせられる。そんな、高台の街なので、その昔、水資源確保は大変だったと言う。
上野原は昔も今も高台にある街だ。街の中心地は甲州街道(国道20号)にあるが、桂側沿いの中央線からははずれている。駅と街はバスで行き来するが、これを歩くとなると結構疲れさせられる。そんな、高台の街なので、その昔、水資源確保は大変だったと言う。木食白道加持水井
 上野原は昔も今も高台にある街だ。街の中心地は甲州街道(国道20号)にあるが、桂側沿いの中央線からははずれている。駅と街はバスで行き来するが、これを歩くとなると結構疲れさせられる。そんな、高台の街なので、その昔、水資源確保は大変だったと言う。
上野原は昔も今も高台にある街だ。街の中心地は甲州街道(国道20号)にあるが、桂側沿いの中央線からははずれている。駅と街はバスで行き来するが、これを歩くとなると結構疲れさせられる。そんな、高台の街なので、その昔、水資源確保は大変だったと言う。
江戸寛政期(1700年代末期)に木食白道(もくじきびゃくどう)という僧がこの地を訪れた。木食とは、5穀を絶ち、木の実で生活することで、この訓練をすることを木食行、木食行をする人達を木食上人と言っていた。穀とは、米・麦・アワ・キビ・豆などのことで、これらを食べずに木の実など野山の恵みだけで生活するという言わばサバイバル訓練の一種といえる。しかし、木食上人達の最終目的は、即身仏になること。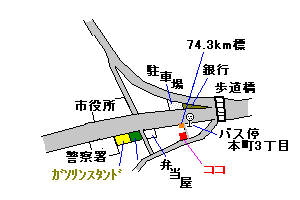 即身仏とは、生きたまま穴に入ってじっとしてそのままミイラになるというものである。うまくミイラになれるように汚れた(と思っていたもの)は口にしなかったのではないだろうか。白道はそんな江戸期に多数存在した木食上人の一人である。
即身仏とは、生きたまま穴に入ってじっとしてそのままミイラになるというものである。うまくミイラになれるように汚れた(と思っていたもの)は口にしなかったのではないだろうか。白道はそんな江戸期に多数存在した木食上人の一人である。
白道が上野原に来た時、水に困っている人々のために祈祷した。そして、村人達は井戸を掘った。白道は井戸が掘り終わるまでこの地にとどまり、仏様をたくさん掘って人々に与えたと言う。この木彫りは、大黒天や恵比寿であることが多く、にこやかに笑っている。称して”微笑仏”と呼ばれている。そんな白道が江戸期の上野原の人々を助けた井戸が今でも残っている。「木食白道上人加持水井」という。
上野原の中心地から国道20号を大月方面に行くと道が3本に分かれる。本線は真中。左の狭い道を50mほど進んだ右手、民家の敷地にその井戸はある。また、近くには上野原警察や上野原市役所もある。何故か、この地が人助けの聖地のように感じてしまう。
寛政9年(1797年)と刻まれた碑のある、その井戸の前に立つと不思議な気分にさせられる。近くにはバス停もあるが、バスで訪れるより歩い来るのがよい。駅は川沿いにあるが、井戸は高台にありそこそこ登らされる。自分の体で当時の人々の苦労を感じ取ることができ、水のありがたみ、井戸のありがたみを知ることができる。井戸の近くには柿の木があり、秋になると実をつけ、命の尊さを教えてくれている。白道48才。
 |
白道の名の残るこの井戸は、上野原と言う街を知る名所のひとつだと思う。 |
さて、この木食白道は20年間ほど大月市鳥沢に住んでいた。白道の住居跡や墓石があるというので、訪ねてみたがはっきりしない。JR鳥沢駅を出て国道20号を渡り、扇山登山の標に導かれていく。高速道路をくぐり、鳥沢幼稚園を右に見ながら道は湾曲して進む。左手に日当たりのよい畑地を眺めながら進むと、正面に堰堤が現われ道は左にヘアピン状にカーブしてゴルフ場・扇山登山口を目指す。この、道がヘアピンカーブしたところに、登山者の安全を見守るかのように平成七年の日付のついた「木喰上人大秀白道行者之塔」が建っている。ゴルフ場・扇山登山口まで歩いてみても、白道が暮らしていたことを示すものは見られない。
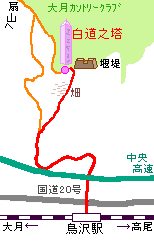 |
 |
「白道之塔」のまわりは、ゴミがちらっている。残念なことに、この林道は全体的にゴミが散らかっている。ビン、カン、ペットボトル、ビニール、吸殻、アメの小袋、食べ終わった弁当など、あるわあるわ。拾ってみると、スーパーの袋一杯になってしまう。これらのゴミはかなり汚れているので、数日ではなくかなり長い間放置されていたと思われる形跡が残るゴミだ。”環境”が注目されている21世紀、18世紀に命を伝えてきた白道はきっと嘆いているとこだろう。 |